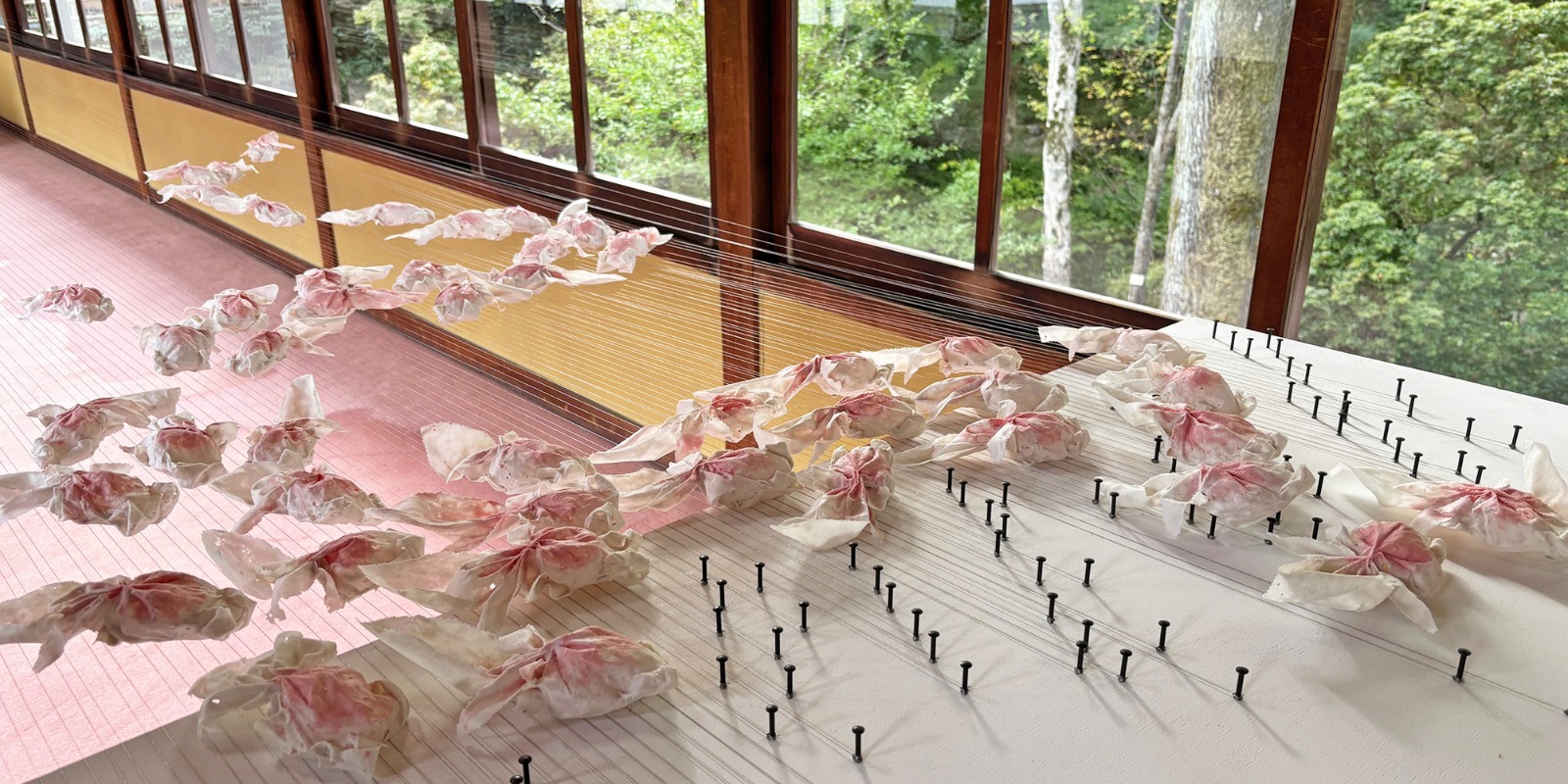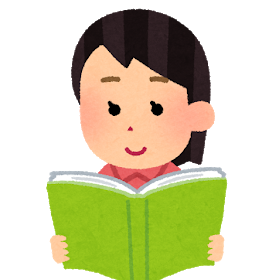株式会社グローバルゲート公式ブログ
東大寺二月堂の修二会が始まりますよ~

こんにちは、グローバルゲートのナミーです。
今季最強寒波で震えてたのに、3日後には3月下旬の暖かさで、身体が対応しきれない今日この頃。皆様、体調を崩されていませんか?
そして、花粉も本格的に飛び始めましたね。
私は今のところまだ症状が出ていませんが、今年は花粉の飛散量が多いとのこと、そろそろ薬を飲むべきか…悩み中です。
最近の花粉症の薬は、眠くなりにくいと書いてますが、それでもやっぱり眠くなるんですよね。
まぁ「春眠暁を覚えず」ですから、飲まなくても眠いのかもしれないんですが。
さて、身体改造計画から1ヶ月が経ちまして、1ヶ月で変化はあったかな?
この1ヶ月の運動量は…
+ 去年よりはジムに行く回数を増やした。
- 寒すぎて外出を極力控えたため、日常生活で身体を動かすことが少なかった。
というわけで、プラスマイナス0 かもしれない…。
1ヵ月の記録として、再度、体組成測定をしてみました。

2日に1回ペースでジムに行ってたんですけど…、この変わらなさよ。
どれか1つぐらい、標準域に入ってもいいのでは…。
ミネラル量に至っては減ってるし、何をしたらミネラル量が増えるのかもわからない。
1年間まじめにジムに通ったら、全部標準までいけるだろうと思ってたけど、1ヶ月でこんなに変わらないなら、難しく感じてきました。
何をしたら良くなるの?もっと運動量増やさないとだめ?プロテインを飲んだ方が良いんだろうか?
とにかくまずは、筋肉量を増やしたいので、今から「鶏の胸肉」買ってきます。。。
奈良県民の3月の行事と言えば、東大寺二月堂の修二会。
「修二会」と言うと、ピンとこない方もいらっしゃるかもしれませんが、「お水取り」と言えばわかりやすいでしょうか。
二月堂を大きな松明が走り抜ける「お松明行事」も有名ですよね。
お松明もお水取りも、修二会の行事のひとつですが、なぜか「お水取り」の方が名称として有名ですよね。
奈良の人は「お水取りが終われば暖かくなる」と、「暑さ寒さも彼岸まで」の代わりに言うので、お水取りの方が馴染みがあるのかもしれないですね。
2月下旬から、修二会行事は始まっていますが、修二会の本行は、3月1日~14日まで。
今からでも間に合います、修二会を体感したい方、ぜひ参考にしてください。
ではまず、修二会って何?って話ですが(←去年の私)
修二会が大好きな友達に誘われて(そんな友達がいるのもレア!)、お松明が観れたらいいわ~ぐらいの気持ちでついて行ったのですが、お松明が全てじゃないから!と、修二会とはなんぞや?をしっかり叩き込んでいただきました。
ざっくり言うと、修二会とは「11人の練行衆(僧侶)が、二月堂の本尊の十一面観世音菩薩(秘仏)の前で、日頃の過ちを懺悔する行(ぎょう)」です。
ざっくり過ぎて随分軽く聞こえますが、約2週間、我々からすると、ストイックすぎる「行」が詰め込まれていまして、しかもそれが、天平勝宝4年(752年)から一度も絶やすことなく続いていると言うんですから、さすが歴史の東大寺!でございます(2025年の修二会は1274回目です)
練行衆の発表(昨年12月16日)は、ニュースでも放映されていたので、今年の大導師は森本公穣さんなのか~と思いながら見てました。
以前に、森本先生のお話を大仏様の目の前で拝聴する機会に恵まれまして、とても素敵な(陳腐な表現ですいません)僧侶だなぁと思っていた次第。
その森本僧侶が、大導師(修二会全体を統括する役)なんだぁ~~~。
・・・おっと、話がマニアックになりすぎそうなので、話を戻します。
「行」のほとんどが、二月堂の中で行われるので、一般観光客はその「行」を見ることはできません。
でも、どうしても二月堂の中が気になるという方!覗き見してください。
覗き見と言うと聞こえが悪いですが、見てもいいんです。全体が見えるわけではないので、格子越しに「覗き見」するといった感じにはなりますが。
お堂の手前に畳の部屋(局)がありまして、そこに入ると、読経の声、僧侶が走る下駄の音等が、響いてきます。
この堂内での「行」を聴聞してこそ、修二会を拝見した!と言えるのではないかと思います。
私は、お松明よりも感動しました。
でも、日中ずっと「行」が行われているわけではありませんので、ご注意を。
(日によって「行」の内容と時間が多少異なりますので、スケジュールを確認して二月堂に向かわれてください)
日中~夜中にかけての「行」で拝見できる、私のおすすめをご紹介します。
正午になると食堂(じきどう)において「食堂作法(食事)」があります(練行衆の食事は1日1回)
↓食堂にご飯を運ぶところ

おすすめは、食堂から練行衆が出てくる時に行われる「生飯(さば)投げ」
練行衆が取り分けたご飯(生飯)を、紙に包んで、食堂向かいの閼伽井屋(あかいや ※お水取りの水を汲み上げる場所)の屋根に投げ、鳥獣にも施しを…という儀式です。
どこで見てたのか、生飯投げが始まったら、すぐにカラスと鹿がやってきました。奈良の鳥獣は、修二会に精通してるようです。
↓生飯投げの様子。手前にあるのがお松明です。

生飯を投げるフォームがかっこいい僧侶がいたので、友達に「今の僧侶、投げ方がプロやね」と話したら、「あの僧侶は昔野球やってはった」と。
さすが修二会のプロ、情報量が半端ない!
午後1時頃。練行衆が二月堂に上堂します。

ピリピリした雰囲気なのかと思っていましたが、軽快な足取り?!でした。
さすがは、精鋭なる練行衆、今から始まる「行」も、苦とは思ってらっしゃらない様子。
堂内で、日中・日没の法要を行われている間、我々一般人は局からの聴聞を堪能したら、一旦二月堂を離れましょう。
(日中・日没の法要の後は、練行衆は参籠宿所へ下堂され、仮眠・入浴等の休息時間です)
そして、再び午後7時に入堂される時が、あのお松明行事なんです(僧侶の入堂の明かりとしてのお松明)
お松明を良い位置で観たい方は、練行衆の下堂前から並び始めています(午後2時にはすでに並んでる方がいらっしゃいました、特に土日は混むのでお早めに)

そんなに早くから並べないよ~という方には、この時間の間に、東大寺や東大寺ミュージアム、奈良国立博物館(この時期はお水取りの展示があります)がおすすめ。
私たちは、寒かったので、喫茶店で一服して、二月堂近辺の散策(歩いて身体を温める作戦)に出かけました。
東大寺の周りはお寺がたくさんあり、そのお寺の門に、輪っかのしめ縄をいくつか見かけました。
これ、何かかわかりますか?

輪注連(わじめ)と言って、練行衆の自坊の門にかけられるものです。
ちなみに、修二会が終わると、境内の木にかけるそうです。
再び二月堂に戻ってきたのが4時前。列は増えていましたが、この人数だったら、二月堂下の芝生(竹柵内)に入れるでしょう。
それから17時までの1時間、寒い中ひたすら待ち、17時にようやく二月堂の下(良い位置!)へ誘導してもらえました。
二月堂の下は結構急な斜面なので、事故が起きないよう、人数制限をして誘導されています。
それからの2時間が、地獄でした(特に日が暮れてからの1時間強、寒くて即身成仏しかけました…)
なんせ寒い…。じっとしてるからなおさら寒い。あらゆる防寒具を身につけて、ひたすら耐える…。
↓待機中の友達、お松明の火の粉を被る位置なので、この2人は防火用の上着を着ています。

ちなみに、ゴミ袋の中に看板を入れて、火の粉対策。待ち時間の折りたたみ椅子も必須です(腰が痛くなるよ)
日が暮れてきた頃には、二月堂の外にも人が溢れていました。

寒さに耐えて耐えて、ようやく午後7時の東大寺の大鐘が鳴り、お松明が点火。

階段を登ってくるお松明と、二月堂の欄干から火の粉を撒き散らすお松明。
この火の粉を浴びると健康に過ごせると言われているので、しっかり浴びておきましょう~!
この大きなお松明を持って走り抜ける、練行衆の補佐役「童子」は、体力ないとできないですね、なんせ重さは60kgもあるんですから。
12日の籠松明に至っては、80kgですよ!
この日は合計10本のお松明が駆け抜け、火の粉もしっかり浴びて、お松明を堪能しました。
この後、堂内では深夜まで作法が続きますが、私たちはこれにて終了。寒くて限界、暖かいお店に直行しました。
日を改めまして、3月12日。
一番大きな籠松明の日で、この日しかお松明をやっていないと思っている方が案外たくさんいらっしゃるので、ものすごく混雑します。
昨年の3月12日は平日だったので、仕事が終わってから向かったのでは間に合わないので諦めましたが、友達の情報では、18時の時点で、すでに長い列ができていて、この先並ばれても見れない可能性があります。と何度もアナウンスが流れていたそうです。
お松明が走り抜けると、どっと列が流れるので(1回観れたら移動させられます)、友達は無事見れたそうですが、最後の方の人は無事見れたのかな?やはり12日は、大人気ですね。
どうせ見るなら、欄干に横一列10本のお松明が並ぶ、14日が見応えあるかなと思います。
籠松明はパスした私は、仕事が終わってから二月堂へ駆けつけました。
すでに総勢8人の友達が集合。ありがたきマニアックな友よ。
12日深夜(13日の午前1時)、お水取り行事が始まりました。
篝火(かがりび)と笙等の奏楽の中、ゆっくりと二月堂の階段を降りてきた、お水取り御一行様。

閼伽井屋で御香水を組み上げて、またゆっくりと階段を登り(これを3往復)、二月堂内陣に御香水を納められます。
笙の音色が響いていたので、仏事と言うよりは、神事のようでした。
↓階段を登る様子を横から。とても神秘的でした。

↓二月堂に御香水が納められる様子。階段を登っている時の神秘的な様子と比べると、随分わちゃわちゃしてました。

お水取りが終わった頃には、深夜2時半を過ぎていましたが、ここまでいたんだから、作法も最後まで観ましょうよ!と言うことで、局内で4時まで聴聞しました。
この日は「達陀(火の行)」があり、堂内を松明を持ってぐるぐる歩き回るわ、火の粉は飛び散るわで、燃えないか心配で眠気も吹っ飛びました。
1300年近く続いてきて、よく今まで燃えなかったなぁと、驚くばかり。
(江戸時代に一度燃えていますが、この達陀の火が原因ではなかったそうです)
想像を超える火の量ですよ、ほんとに!
局からは全ては見えないので、帰ってから東大寺公式チャンネルで達陀の様子を拝見して、こんな風に行われてたんだ~と再び感動。
興味のある方は、ぜひ見てみてください。
午前4時、この日の「行」が終了し、下堂の様子。

この時、練行衆は「手水(ちょうず)、手水~」と言いながら降りていきます。
手水とは、お手洗いのこと。
「トイレに行ってくるから~!すぐ戻ってくるから~!」と、天狗に言ってるそうです。
その昔、練行衆が下堂している隙に、天狗が二月堂に悪さをしたから、すぐ戻って来るよ!アピールをして、悪さを防ごうとしてるんだとか。
「行」の最後が、おちゃめな終わり方でした。
さぁ、みなさんも行きたくなりましたか?
私は今年も、深夜のお水取りを観に行きたいと思っています。
明日からの本行、無事、満行されますように。
いつも、ホームページ更新ソフトwebchangerのご案内をしていますが、今回は、データを守るGSVのご紹介です。
修二会が始まった752年に、データ保存の技術があれば、1273回分の修二会の記録が残ってたのになぁと、ないものねだりですが残念に思います。
でも、データを安全に確実に残さないと、せっかく保存しておいたデータも、消えてなくなってしまいますからね。
自動バックアップやRAID構成による多重保存が可能なGSVで、未来にデータを残しませんか?
データのバックアップにお悩みの方、ぜひお問合わせをお待ちしております。
【関連記事】